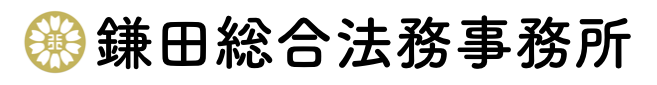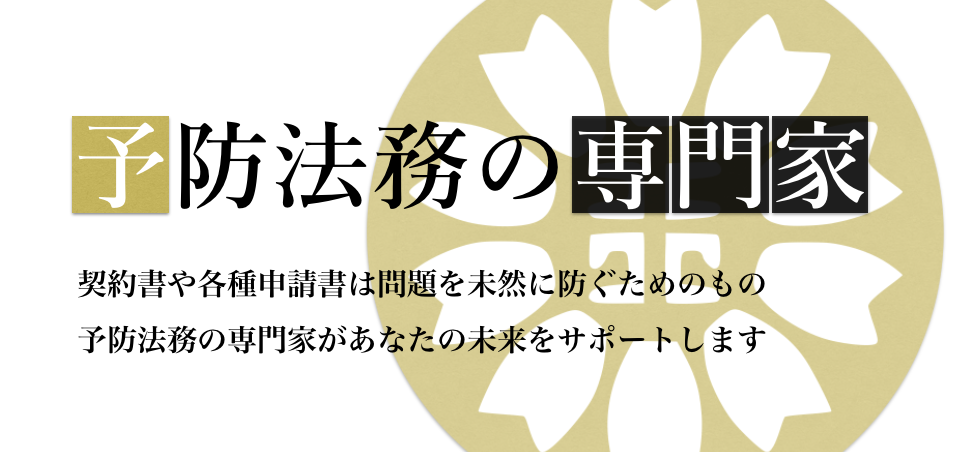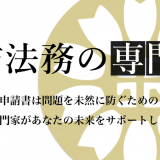会社を設立することは人生において大きな決断です。法人化することのメリットをしっかりと踏まえて次のステップに備えましょう
① 対外的な信用度
会社は商号、住所、目的代表者、資本金、役員等が登記されると、情報が一般的に公開されるため個人事業主よりも信用を得られます。
特に大手企業は実績があっても個人事業主へ仕事を発注しない会社が多いです。
個人のお客さんからしましても頼む相手が個人よりも会社の方が信頼して依頼をしやすいという心理が働くと思います。
肩書や名刺に「株式会社」とあるだけで、取引先の印象がかなり違うということも理解できると思います。
とはいえ、株式会社も資本金1円から設立できるため、必ずしも個人より会社の方が信用があるというわけではありません。
事業形態によっては個人でも十分信用を得られるものもあります。
しかしながら、同じ業種であれば、個人よりも会社の方が信用面で有利になるのは明白です。
② 節税面で有利
個人事業主では所得が増えるほど税率が高くなる累進税率で課税されますが、法人税は利益が増えても原則一定税率で課税されます。
その為、売上が大きい場合は法人税が有利になります。
加えて会社の方が経費にできる費用が多いため税制面で有利です。
個人事業主の場合は、売上から必要経費を差し引いた残り全部が自分の所得になります。
会社の場合は、会社が自分に役員報酬という形で給与を支払う形になります。
役員報酬を含めて給与として貰うお金は、会社の売上から必要経費を差し引いた金額から、給与所得控除といって役員報酬の一定割合を必要経費とみなして所得から差し引くことができます。
つまり自分に支払った給与も経費として計上できるため節税できる可能性が高くなります。
具体的な金額で考えますと、年間所得が400万円を超えるようになってくれば法人化を検討した方がよいでしょう。
税務上のメリットは次のようなものがあります。
給与所得控除が使える
上でも記載している通り、会社から役員報酬をもらうと、売上から必要経費を控除した金額から、さらに給与所得控除(報酬額の一定金額を必要経費として所得から控除する)ができ、課税される所得を小さくすることができます。
所得税と法人税の税率の差
個人事業主の所得税は所得が増えれば増える程、税率が高くなっていく超過累進課税です。
法人の税率は一定なので、所得が増えてきた場合は会社設立による節税効果は高くなります。
経費として認められやすい
個人事業主の場合は家計用と事業用の線引きが曖昧なので、事業用として必要経費に認められにくくなります。
一方、会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみるという前提があります。
この為、法人にした方が会議費や交際費、自宅兼事務所、自動車、生命保険料、退職金など、経費として認められる幅が広くなります。
9年間欠損金を繰越すことができる
ある年度で損失が出た場合、その損失を翌年度以降の所得と相殺することができます。
これを欠損金の繰越控除といいます。
個人事業主の場合は純損失の繰越は3年間ですが、法人の場合は青色欠損金を9年間繰越すことができます。
消費税の免税効果
個人事業主でも法人でも創業時の2期間(2年間)は消費税が原則としてかかりません(第1期の半年間の売上と給与等の金額がいずれも1,000万円を超える場合や、資本金が1,000万円以上等は例外)。
その為、個人事業主で創業してから2年後に法人を設立すれば、最長で4年間の消費税の納税を免除されることになります。
家族への給与
個人事業主は原則として家族に給与を支払うことができません(青色事業専従者給与として届出をした場合は例外)。
法人の場合は実際に事業に従事していれば、家族に対して労働の対価としての相当額を給与として支払うことができます。
所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することも可能になります。
③ 資金調達に有利
個人事業主は金融機関などでの融資条件が会社よりもかなり厳しくなります。
その他にも、最初から個人事業主では利用できない融資もあります。
個人の場合、貸借対照表が免除されている為、金融機関は融資審査の際に返済能力の有無が判断しづらく、法人に比べて融資条件が厳しくなります。
その為個人事業主で金融機関から融資を受けようとする場合、第三者保証人を要求されます。
法人の場合は、損益計算書と貸借対照表が作成される為、金融機関も融資判断が明確にでき、融資の可能性が増加します。
④ 人材調達に有利
個人事業主の下で働くよりも、会社の正社員として安定的な雇用を求める人が多くなっています。
大企業で働いていたような優秀な人材であればこそ個人事業主のもとに応募してくる可能性は高くはないでしょう。
⑤ 自由に決算日を設定可能
個人事業主の事業年度は1月〜12月と定められています。
法人の場合は決算日を自由に決める事が可能です。
忙しい時期に決算事務が重ならないように調整して、業務負担を平準化することが可能です。
⑥ 事業承継がしやすい
個人事業主では、事業主が死亡すると相続関係の為に、個人名義の預金口座が一時的に凍結される事があります。
このタイミングと支払時期が重なってしまうと事業に支障が出る可能性があります。
法人化すれば会社の資産が相続の対象となることはありませんので、代表者に死亡による会社の預金口座の凍結や、事業がストップすることはありません。
また、会社の場合は代表を変えるだけで事業継承できるため家族に事業を引き渡すのも簡単です。
⑦ 個人資産が差押えを受けない
個人事業主の場合、借入金や仕入れ先への未払い等は事業主名義で成されている為、事業主が返済しなければなりません。
また、事業主が死亡した場合はその負債は相続の対象になり、家族が支払いをする可能性もあります。
法人の場合は出資の範囲内での責任にとどまりますので、会社が破産した場合でも形式的には個人に返済義務はありません。
但し、中小企業の場合、金額の大きな借入については社長個人が連帯保証人になることを求められる場合があるので、このような場合は返済義務が発生します。