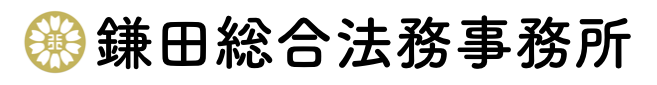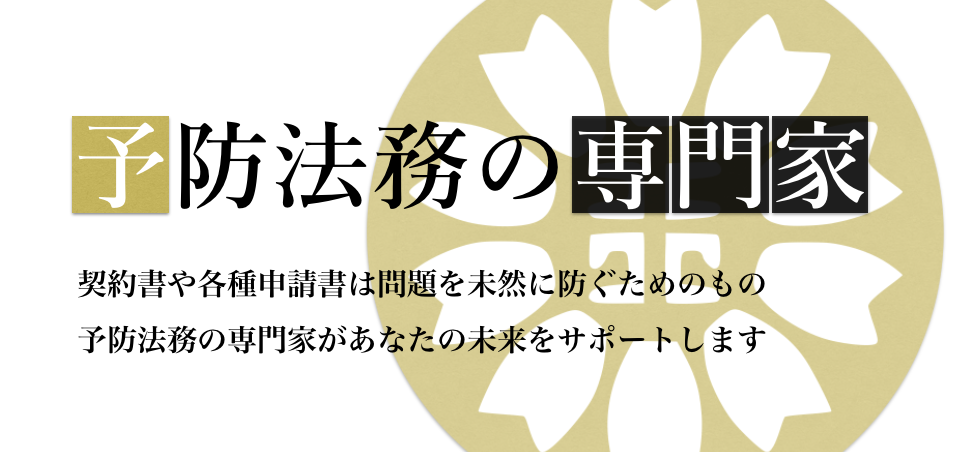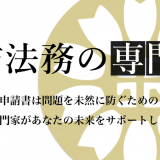電子契約書についての誤解
電子契約書は紙の印刷や郵送が不要な点や印紙の貼り付けが必要ないという点でメリットがあります。
しかし電子契約書について調べると、様々な外部サービスがあって採用を保留にしたり諦めた方も多いと思います。
電子契約書には誤解しやすいポイントがあるのでそこを簡単に説明します。
特に小規模ビジネスを展開している事業者の方は必見です。
電子契約は外部サービスを必要としない
まず初めにほとんどの小規模ビジネスの電子契約に外部サービスは必要ありません。
メールでPDFの契約書を相手方に送って、名前を入力してもらって返信を受ける。
これで電子署名法上でも正式に契約は成り立ちます。
ではなにが電子契約を難しくしているのでしょうか。
これは「電子署名」が電子契約を分かりづらくしています。
電子署名とは
電子署名とは、電子文書(PDFやWordファイルなど)に対して、署名者がその文書の作成や承認に関与したことを示すデジタルな形式の署名です。
例えばオンラインサービスを利用する際に、利用規約等に同意して、名前を入力して利用者登録をしますが、それも電子署名の一つになります。
サービス利用のためのアカウント作成も立派な電子契約の一つです。
ただし、電子署名には三文判程度の証明効果しかありません。
誰でも他人の名前を書けてしまう電子署名では、その署名が当事者本人のものであることを証明するのが難しく、また、電子契約書は簡単に改竄できるため、署名後に契約内容が変わっていても判断が付きません。
そこでより証明力を強める為に使われるのが「認証された電子署名」になります。
認証された電子署名とは
認証された電子署名とは、認証局が署名者や署名日時を保証するため、法的効力を持つ署名として認められます。
ただし、認証された電子署名にも「証明力」に強度があり、一般的な企業の認証と公的な認証局の認証では大きく異なります。
簡単に説明すると以下の特徴があります。
一般的な企業の認証サービス
- 当該企業のアカウント認証を必要とされる
- アカウント作成時に身元確認は行われない
- 認証業務に主務大臣からの認定がない
例えば、A会社の認証サービス利用者「鈴木」のアカウントから署名がされたことは証明されるが、「鈴木」が本当に「鈴木」なのかまでは分からない。
証明力は良くても認印レベル
認定認証事業者の認証サービス
- 認定認証事業者のアカウント認証を必要とされる
- アカウント作成時に公的身分証等による身元確認を行なう
- 主務大臣が認定した事業者が認証
銀行やマイナンバーカードを利用する公的機関の行う認証サービスがこれにあたります。
証明力は実印+印鑑証明書レベル
証明力まとめ
- 一般的な名前入力による電子署名
三文判レベル - 一般企業の認証サービスによる電子署名
良くても認印レベル - 認定認証事業者の認証サービスによる電子署名
実印+印鑑証明書レベル
電子署名よりも契約内容に重点を
電子契約を結ぶ際に認証された電子署名を使うのが望ましいのは確かですが、ほとんどの小規模ビジネスに認証された電子署名は必要ありません。
紙の契約書を使った場合に、どの程度の証明力を求めるかを考えてから外部サービスを利用した方がいいです。
結局の所、電子署名の証明力の話は裁判になるほど揉めた時です。
そして往々にして揉めるのは圧倒的に契約内容が原因です。
契約書の改竄が不安であれば、タイムスタンプやメールの送受信履歴を控えることで署名日時の証明ができ、改竄を防げます。
契約相手の素性が不安な場合は簡単に契約せずに話し合いを持つのは紙の契約書でも同じです。
電子契約の一番の問題点は、企業などが提供する契約書のテンプレートをそのまま利用してトラブルリスクを高めることです。
事業に適した契約書を作成することでトラブルを事前に回避することが大切です。
契約書のご相談は当事務所にお任せください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
いただく情報は以下のみでも結構です。
①どのような契約書が必要か
②盛り込みたい内容、疑問点など
③締結したい時期
内容、ボリュームに応じて個別にお見積もりをお出しいたします。